「くらしの足をみんなで考える全国フォーラム2015」

2015年10月24日(土)、25日(日)の2日間にわたり「くらしの足をみんなで考える全国フォーラム2015」が、東洋大学(東京都文京区)で開催されました。
全国から多くの方々にご参加いただき、ありがとうございました。

今年で第4回目の開催となった「くらしの足をみんなで考える全国フォーラム2015」(於:東洋大学白山キャンパス1号館(東京都文京区白山5-28-20)主催:くらしの足をみんなで考える全国フォーラム実行委員会/実行委員長:岡村敏之氏(東洋大学教授)、副実行委員長:加藤博和氏(名古屋大学准教授) 共催:交通エコロジー・モビリティ財団 協力:東洋大学 後援:国土交通省、厚生労働省、全国社会福祉協議会、東洋大学国際共生社会研究センター、日本民営鉄道協会、日本バス協会、全国ハイヤー・タクシー連合会、全国個人タクシー協会、全国福祉輸送サービス協会、DPI日本会議、市民福祉団体全国協議会、全国移動サービスネットワーク メディアパートナー:(株)東京交通新聞社))。
ご参加いただいた方は、24日・25日の2日間で約260名(事前予約:224名、当日参加:40名)にのぼりました。

現在、日本では過疎地域や被災地のみならず、都市部においても高齢者や障がいのある方々、通院、買い物など生活のための最低限の外出に困難を抱える人たちが増えています。
本フォーラムは、このような我が国の「くらしの足」の問題について、どのように解決するかを利用者・生活者の立場で語り合うための場として始まりました。
そして本フォーラム第4回目となる今年も、全国から「くらしの足」の問題を共有する人たちがそれぞれの立場、考え方で自由に話し合い、集まる「場」をともに作るためにご参加くださいました。

特に学生の皆さんのご協力・ご参加や、若い世代の参加者のエネルギーは、これからのフォーラムの継続にとって、“大きな力”となる兆しを感じさせてくださいました。
また、第1回目から継続してご参加くださっている方々ならではの“経験”や“課題”“事例紹介”などのお話は、参加者一人ひとりにとって新たな“気づき”や“挑戦”につながったことと思います。
本フォーラムの副題である、「移動の問題」を本音で語り合おう、知り合おう、そして「一歩踏み出そう」の想いのもと、2日間、多くの方にご参加・ご協力いただき、無事に終了いたしましたことに、心から御礼申し上げます。
【1】「くらしの足をみんなで考える全国フォーラム2015」について
「くらしの足をみんなで考える全国フォーラム2015」では、多くの人たちがそれぞれの立場から「くらしの足」の問題解決に取り組む「実践」の流れを作っていくことをめざしました。
過去3回のフォーラムで取り上げられ、語り合った問題や課題に対して、新しく作られた法律や制度、またインターネットの利用や全国の事例など、さまざまな「情報交換」と「意見交換」を目的に、①セミナー ②ワークショップ ③基調講演 ④ラウンドテーブル ⑤ポスターセッション ⑥懇親会 を大切な「コミュニケーションの場」として設定したのが特徴です。
特に今回のフォーラムでは「そして『一歩踏み出そう』」に実行委員会のメッセージを込め、解決のための一歩をどう踏み出すか、さらなる高みをめざすためにどこに一歩を踏み出していくかを目前のミッションとして開催されました。
【2】プログラム
◆<第1日目 10月24日(土) セミナーとリレートーク・ワークショップ>
●開会:主催、来賓挨拶
岡村実行委員長 全体司会・篠原氏
●セミナーとリレートーク:くらしの足を地域はどう守るのか、どう育てるのか
「くらしの足」はなぜ必要か? くらしの足を支える「三方よし」をどうデザインするか? が、登壇者それぞれの事例紹介をもとに話し合われました。
またこのテーマは、引き続き行われた「ワークショップ」において議論されました。
講 師:吉田 樹氏/福島大学 経済経営学類 准教授
司 会:福本 雅之氏/豊田都市交通研究所研究部 主任研究員
登壇者:
菊地 良三氏/福島県若松市金川町・田園町住民コミュニティバス運営協議会
若菜 一繁氏/千葉県市原市企画部交通政策課
岩村 龍一氏/(株)コミュニティタクシー(岐阜県多治見市)取締役会長
井口 清一郎氏/袖ヶ浦市NPO法人たけのこ「平川いきいきサポート」専務理事


●ワークショップ:参加者が20のグループに分かれて、「住民・自治体・交通事業者~三方よしのつくり方」について語り合いました。
「三方よし」が難しいのは、お互いが何を求めているのかわからないからではないか? という想いから「自分が何を求めているのか」「相手は何を求めているのか」を話し、発見する場として自己紹介、ディスカッション、発表が行われました。








●懇親会:
初日のプログラム終了後、会場となった東洋大学白山キャンパスの食堂において懇親会が開催されました。
主催者側及びご来場いただいた皆様との情報交換及び親交を深める場として和やかな時間を過ごされました。
また、会場設営や受付等でお手伝いいただいた東洋大学の学生達も改めて紹介され、ねぎらいを受けました。
◆<第2日目 10月25日(日)基調討論・ポスターセッション・ラウンドテーブル>

●主催、来賓挨拶


岡村実行委員長 二村会長


蒲生部長 藤井局長
●基調討論:「みんなで地域公共交通網を組み上げ、お出でかけしやすい地域をつくりだそう」
「くらしの足」確保のための活動は個別では限界があるため、目的意識を共有して互いを尊重し、役割分担し連携して取り組んでいくことが重要です。
「基調討論」ではさまざまなお立場の方に集まっていただき、これまでの取り組みや現状認識についてご紹介いただいたあと、「どう『一歩踏み出すべきか』」が話し合われました。
登壇者:松本 順氏/(株)みちのりホールディングス代表取締役
川鍋 一朗氏/日本交通(株)代表取締役会長
谷島 賢氏/イーグルバス(株)代表取締役
嶌田 紀之氏/千葉県南房総市企画部企画政策課副主幹
清水 弘子氏/(特非)かながわ福祉移動サービスネットワーク理事長
大野 悠貴氏/弘前大学学生団体 H・O・T Managers代表
司 会:加藤 博和氏/名古屋大学大学院環境学研究科准教授・交通政策審議会委員






冒頭、司会の加藤先生より説明があった通り、今回の基調討論は「貴重討論」ともいえる豪華メンバーが集まって満席の聴講者の中での討論会となりました。
それぞれの登壇者の方々からの発表及び討論の後、全員より今後の活動についての約束をメッセージに書いていただきました。登壇者の中にはお一人で何枚もお書きになった方もおり、皆さんの強い意志が伝わりました。
*「基調討論」終了後、登壇者の皆様よりメッセージをいただきました。(順不同)


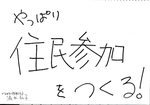








●ポスターセッション:くらしの足を守る全国の皆さんの取り組みをパネル展示。貴重な対話の時間が生まれました。
・おでかけを支援する技術:階段昇降機やパーソナルモビリティ、自動運転車両等の実用化の課題など
・生活支援総合事業を考える:厚労省の生活支援総合事業をくらしの足に活用するための課題など











●ラウンドテーブル:登壇者を中心に参加者も意見交換。参加するテーマは自由に選択できるため、会場を行き来したり、じっくりと参加して発言することが可能になりました。

①「くらしの足」を守るために市民はどう一歩踏み出すか
地域交通を自分たちの課題としてとらえ住民と行政や交通事業者はどう協働できるのか、持続可能な事業者は何か、1日目のリレートークを掘り下げました。
[アドバイザー] 吉田 樹氏 (福島大学)
[司会・進行] 鬼塚 正徳氏((特非)せたがや移動ケア)
[話題提供者] ・武田 康弘氏(徳島県つるぎ町まちづくり戦略課)
・谷田貝 哲氏(バスマップ沖縄 主宰)
・齋藤 富夫氏((特非)かみのやま福祉運送サービス)

②地域公共交通網をみんなで組み上げ一歩踏み出すために
くらしの足(地域公共交通網)を組み上げるための実務はどのように進めるのか、地域をまたがる交通問題の調整、住民参加やコンサルの活用などを話し合いました。
[アドバイザー] 大井 尚司氏(大分大学)
[司会・進行] 嶌田 紀之氏(千葉県南房総市企画部企画政策課)
[話題提供者] ・野中 智弘氏(福岡県企画地域振興部交通政策課)
・岩村 龍一氏((株)コミュニティタクシー)
・猪嶋 宏記氏(福井県総合政策部交通まちづくり課)
・岡本 英晃氏(交通エコロジー・モビリティ財団)

③タクシー事業は未来へどう一歩を踏み出すのか
くらしの足は誰が担うのか、子育て・キッズ・陣痛タクシーを一例にして、個別輸送のタクシー事業者を中心に、鉄道、バス、NPOも参加し意見交換しました。
[アドバイザー] 福本 雅之氏(豊田都市交通研究所)
[司会・進行] 及川 孝氏 ((有)フタバタクシー)
[話題提供者] ・篠原 俊正氏((株)ハートフルタクシー)
・多田 直紀氏(名古屋タクシー協会)
・清水 弘子氏((特非)かながわ福祉移動ネットワーク)

④インターネットやスマホはくらしの足にどう踏み込むのか
くらしの足を確保するツールとして、インターネットやスマホ利用の現状とサービスの可能性、今後の方向性について意見交換しました。
[アドバイザー] 宮崎 耕輔氏(香川高等専門学校)
[司会・進行] 清野 吉光氏((株)システムオリジン)
[話題提供者] ・伊藤 昌毅氏(東京大学生産技術研究所)
・太田 恒平氏(ナビタイムジャパン)
●まとめ・閉会
4つの「ラウンドテーブル」で話し合われたテーマについて、各ラウンドのアドバイザーから報告がありました。


吉田 樹氏(福島大学) 大井 尚司氏(大分大学)


福本 雅之氏(豊田都市交通研究所) 宮崎 耕輔氏(香川高等専門学校)

その後、加藤 博和副実行委員会委員長より、2日間にわたるフォーラムについての「まとめ」がされました。
「『みんなの想い』で地域公共交通を地域の手に取り戻し、役に立つものに現場で変えていきましょう。
住民の想い:必要なおでかけが確保された生活環境。
自治体の想い:豊かで魅力的な地域。
事業者の想い:存在意義があり収益モデル事業運営。
運転手の想い:やりがいがあり苦しくない仕事場。

これらを全部実現することができる、みんなが安心して住み続けられる持続可能な地域を支えうる、みんなが利用したくなる持続可能な公共交通を、みんなで守り育てる体制を作りましょう。
そのためにも「現場起点」が大事! まず現場であなたが動くことから始まります! それぞれの成功体験を大切にして、皆さんで今日“決意”しませんか?」という熱いメッセージとともに次回フォーラムでの再会が約束されました。

続いて、鎌田 実実行委員会顧問(東京大学大学院新領域創成科学研究科教授)より「くらしの足」に関する海外での事例紹介がされた後、「『くらしの足』の問題はもう少し広い目でとらえることが重要です。交通は利用者にとっては移動の手段。そもそも移動とは、交通だけで解決できることではなく限界があります。広くまちづくりの視点で取り組んでいきましょう」という呼びかけがされました。

最後に、鎌田実行委員会顧問から参加者に向けて投げかけられた「また、来年お会いしましょう」という閉会の言葉で、2日間のフォーラムは幕を閉じました。
【3】アンケートから
・専門性を担保しつつも、子連れの参加、車イスでの参加も受け入れられる幅広さが両立できており、こうした場が非常に良いと思った。
・営業職でないため、他企業及び事業者、研究者とセッションできるワークショップは大変有意義でした。
・さまざまな実施形態を知ることができたこと及び現在行っているサービスの拡大、方法等について参考になった。
・間接的ではなく、直接、市民の声を聞きたいです(ゲストで来ていただくか、動画等でも良いので関わりたいと思います)。
・アンチ運動の方々の声を聞きたい。また、厚労省の方の参加をお願いしたい。


フォーラム終了後の実行委員会の委員、関係者。会場となった東洋大学の学生スタッフたち
写真提供:(株)東京交通新聞社、事務局スタッフ
「くらしの足をみんなで考える全国フォーラム2015」
◆趣旨
少子高齢化が進む中で、日常の通院や買い物等に困難を抱える人々が全国で増え続けています。このくらしの足の問題を解決するために、当事者、行政職員、研究者、バス・タクシー事業者、福祉・介護・医療の従事者、NPOなど、多くの関係者が集まり、地域を越え、立場を越え、利用者、生活者の目線をベースとして本音で語り合い、お互いを知り合い、それぞれが抱える問題解決のヒントを得る「気づき」の場として、本フォーラムを開催します。くらしの足の問題を意識し、何とかしたいと考えている皆さん、ぜひご参加ください。
◆開催日:平成27年10月24日(土)~10月25日(日)
◆会 場:東洋大学白山キャンパス(東京都文京区白山5-28-20)1号館
◆参加費:両日参加 4,000円、1日参加 3,000円(当日会場でお支払ください)
◆対象者:300名ほど
(移動の問題を意識し、何とかしたいと考えている方々ならどなたでもご参加ください)
◆<第1日目 10月24日(土) セミナーとリレートーク・ワークショップ>
●くらしの足を地域はどう守るのか、どう育てるのか
講 師:吉田 樹氏/福島大学 経済経営学類 准教授
司 会:福本 雅之氏/豊田都市交通研究所研究部 主任研究員
登壇者:菊地 良三氏/福島県若松市金川町・田園町住民コミュニティバス運営協議会
若菜 一繁氏/千葉県市原市企画部交通政策課
岩村 龍一氏/(株)コミュニティタクシー(岐阜県多治見市)取締役会長
井口 清一郎氏/袖ヶ浦市NPO法人たけのこ「平川いきいきサポート」専務理事
【タイムテーブル】
12:30 受付開始
13:30~13:45 ご挨拶
13:45~15:15 セミナーと実践者のリレートーク
15:30~17:15 ワークショップ
17:30~19:30 懇親会
◆<第2日目 10月25日(日)基調討論・ポスターセッション・ラウンドテーブル>
●基調討論「みんなで公共交通網を組み上げ、お出でかけしやすい地域をつくりだそう」
登壇者:松本 順氏/(株)みちのりホールディングス代表取締役
川鍋 一朗氏/日本交通(株)代表取締役会長
谷島 賢氏/イーグルバス(株)代表取締役
嶌田 紀之氏/千葉県南房総市企画部企画政策課副主幹
清水 弘子氏/(特非)かながわ福祉移動サービスネットワーク理事長
大野 悠貴氏/弘前大学学生団体 H・O・T Managers代表
司 会:加藤 博和氏/名古屋大学大学院環境学研究科准教授・交通政策審議会委員
●ポスターセッション
★くらしの足を守る全国の皆さんの取組をパネル展示。直接対話もできます。
・おでかけを支援する技術
階段昇降機やパーソナルモビリティ、自動運転車両等の実用化の課題など
・生活支援総合事業を考える
厚労省の生活支援総合事業をくらしの足に活用するための課題など
●ラウンドテーブル
★登壇者を中心に参加者も意見交換。参加するテーマは当日でも自由に選択可能。
①「くらしの足」を守るために市民はどう一歩踏み出すか
(アドバイザー)吉田 樹氏(福島大学)
(司会・進行)鬼塚 正徳氏((特非)せたがや移動ケア)
(話題提供者)
・武田 康弘氏(徳島県つるぎ町まちづくり戦略課)
・谷田貝 哲氏(バスマップ沖縄 主宰)
・齋藤 富夫氏((特非)かみのやま福祉運送サービス)
[内容]
地域交通を自分たちの課題としてとらえ住民と行政や交通事業者はどう協働できる
のか、持続可能な事業者は何か、1日目のリレートークを掘り下げる。
②地域公共交通網をみんなで組み上げ一歩踏み出すために
(アドバイザー)大井 尚司氏(大分大学)
(司会・進行)嶌田 紀之氏(千葉県南房総市企画部企画政策課)
(話題提供者)
・野中 智弘氏(福岡県企画地域振興部交通政策課)
・岩村 龍一氏((株)コミュニティタクシー)
・猪嶋 宏記氏(福井県総合政策部交通まちづくり課)
・岡本 英晃氏(交通エコロジー・モビリティ財団)
[内容]
くらしの足(地域公共交通網)を組み合げるための実務はどのように進めるのか、
地域をまたがる交通問題の調整、住民参加やコンサルの活用など。
③タクシー事業は未来へどう一歩を踏み出すのか
(アドバイザー)福本雅之氏(豊田都市交通研究所)
(司会・進行)及川孝氏((有)フタバタクシー)
(話題提供者)
・篠原 俊正氏((株)ハートフルタクシー)
・多田 直紀氏(名古屋タクシー協会)
・清水 弘子氏((特非)かながわ福祉移動ネットワーク)
[内容]
くらしの足は誰が担うのか、子育て・キッズ・陣痛タクシーを一例にして、個別輸送
のタクシー事業者を中心に、鉄道、バス、NPOも参加し意見交換。
④インターネットやスマホはくらしの足にどう踏み込むのか
(アドバイザー)宮崎 耕輔氏(香川高等専門学校)
(司会・進行)清野 吉光氏((株)システムオリジン)
(話題提供者)
・伊藤 昌毅氏(東京大学生産技術研究所)
・太田 恒平氏(ナビタイムジャパン)
[内容]
くらしの足を確保するツールとして、インターネットやスマホ利用の現状とサービ
スの可能性、今後の方向性について意見交換。
【タイムテーブル】
9:00 受付開始
9:30~9:45 主催者、来賓挨拶
9:45~11:45 基調討論
11:45~13:15 ポスターセッション(昼食時間含む)
13:30~15:30 ラウンドテーブル
15:45~16:45 まとめ・閉会
◆主催:くらしの足をみんなで考える全国フォーラム実行委員会
(実行委員長:岡村敏之(東洋大学教授)、副実行委員長:加藤博和(名古屋大学准教授))
◆共催:交通エコロジー・モビリティ財団
◆協力:東洋大学
◆後援:国土交通省、厚生労働省、全国社会福祉協議会、東洋大学国際共生社会研究センター、日本民営鉄道協会、日本バス協会、全国ハイヤー・タクシー連合会、全国個人タクシー協会、全国福祉輸送サービス協会、DPI日本会議、市民福祉団体全国協議会、全国移動サービスネットワーク
◆メディアパートナー:(株)東京交通新聞社(TEL:03‐3352-2181)
◆申し込み方法
当ホームページの申し込み/問い合わせフォームからお願いします。当日参加も歓迎いたします。
◆お問い合わせ先
くらしの足をみんなで考える全国フォーラム実行委員会事務局
〒156-0056 東京都世田谷区八幡山1-7-6 せたがや移動ケア事務所内
Tel:03-3304-5227 Fax:03-3304-5227
E-mail:hasiraserukai@hasiraserukai.com
◆ホームページ http://zenkokuforum.jimdo.com/

 くらしの足をみんなで考える
全国フォーラム
くらしの足をみんなで考える
全国フォーラム




